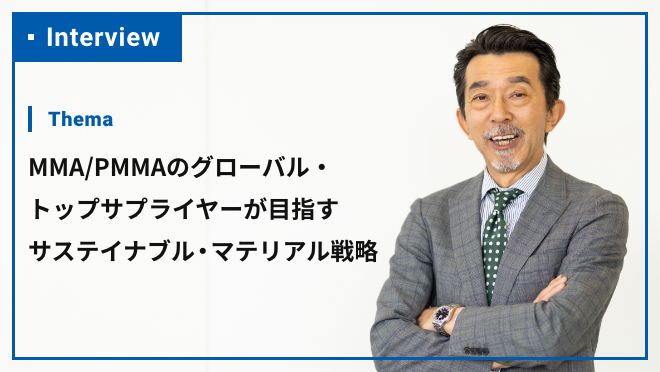
PMMAの特性と広がる可能性「プラスチックの女王」としての魅力とは
― PMMAは、一般的にアクリル樹脂と呼ばれています。透明なプラスチックというイメージですが、具体的にはどのような特性があるのでしょうか。
長谷田:歴史をひも解くと、PMMAが広く使われるようになったのは、第二次世界大戦の頃に戦闘機の操縦席を覆う風防として採用されたことがきっかけです。風防ガラスと呼ばれることもあるのでガラスが使われていると思われるかもしれませんが、アクリル樹脂です。ガラスは大きく無機ガラスと有機ガラスに区分されますが、無機ガラスが一般的なガラス、有機ガラスがアクリル樹脂で、ガラスに比べて割れにくく、軽量で、曲面でも成形しやすいといった特性があります。
また、アクリル樹脂の透明性※)は93%程度で、一般的なガラスよりも透明性が高いことも特徴です。着色すると綺麗に色が付く、つまり、発色性に優れていることも特徴です。こうした特性からアクリル樹脂は「プラスチックの女王」と呼ばれています。透明で発色性も高く、とても美しい素材です。
さまざまな特性から民生用途も拡大し、現在では例えば、透明性と発色性に優れていることから自動車のテールランプ、光をよく通し綺麗な色が出ることからコンビニエンスストアやガソリンスタンドの内照式の大きな看板、コロナ禍のときには飛沫感染防止用のアクリル板などにも大量に使われました。耐候性に優れ紫外線により劣化しにくいという特性もあることからビルディングマテリアル、建材としての用途も拡大しています。
※)透明性:全光線透過率として表現しています

MCGでは、戦前からPMMAの原料となるMMAの製造・販売を開始し、その後、PMMAにも着手、原料から一貫生産しているMMA / PMMAにおける世界のリーディングカンパニーです
― なるほど。さまざまな特性から用途が拡大しているのですね。市場規模はどのくらいなのですか。
長谷田:MCGとして把握しているのは、アクリル樹脂の原料のMMAが世界で約400万トン、アクリル樹脂のPMMAが約120万トンです。ただし、この規模はプラスチック製品の市場規模全体からすると、今はまだ大きいとは言えません。さまざまな特性から用途拡大が非常に期待される素材といえるでしょう。
その視点で今後の成長率をどう予測しているか、MCGでは国や地域のGDPの成長率をひとつの指標として考えています。国や地域によってGDP成長率は違いますが、おおむねGDPの成長率と同程度でPMMAの市場も拡大していく傾向があります。例えば、中国ではGDPが2桁成長をしていた頃には、同様かそれ以上の成長率でPMMAの需要も拡大していました。中国は現在、GDPの伸びがかつてほどではありませんが、大きな市場であることに違いはなく、あわせて、今後はインドなどでの需要の伸びが期待できると考えています。
自動車分野やビルディングマテリアルなど特性を活かした用途への需要拡大に期待
― 期待できる用途は、やはり先ほど説明のあった自動車向けや建材向けが中心でしょうか。
長谷田:やはり、一番は自動車分野です。PMMAはその優れた特性から、従来素材からの代替用途の拡大が進んでいます。例えば、自動車分野でもこれまでは塗装した鋼板やプラスチックが使われていたところに発色させたアクリル樹脂を使うことが進められています。自動車の製造工程において塗装における乾燥工程は高温での作業となることもあってCO₂排出量が多い工程とされています。PMMAに代替すると乾燥工程が不要となり、工数とCO₂の排出量を削減できるのです。

さらに、PMMAはリサイクルがとてもしやすい素材です。最終的に自動車が廃車になっても、PMMAで作られた部材はケミカルリサイクルにより元と同品質のPMMAに戻せます。このように環境負荷低減の視点からもPMMAにはさまざまな優位性があり、その優位性を活かせる自動車分野は大いに期待できる市場です。
また、ビルディングマテリアル、いわゆる建材分野も非常に大きな市場として期待しています。例えば、現在はガラスが使われているところに代替材料としてPMMAが採用される、コンクリートや木材が使われているところにも発色性や耐候性に優れ、リサイクルもしやすいPMMAが利用できるのではないかと期待しています。
その他にもユニークな用途としてはセラミック、陶器の代替材料としての用途も可能性が広がっています。セラミックは重く、加工が難しく、しかも製造工程が高温になるため大量のCO₂を排出することが指摘されています。PMMAなら外観を陶器のように発色させることができるので、見た目はセラミック製品と同様ですが、軽量でリサイクルしやすく、しかも製造工程でのCO₂排出量を抑制できるというメリットがあります。すでに洋式トイレなどで陶器製ではなくPMMAで作ったものが商品化されています。
3つの方向性で環境負荷低減に取り組む
― MMA / PMMAの世界的なリーディングカンパニーとして、環境負荷低減の取り組みも強く求められていると思います。具体的にどのよう取り組みをしているのでしょうか。
長谷田:MCGでは、MMA / PMMA事業における環境負荷低減に大きく3つの方向性で取り組んでいます。まずはケミカルリサイクル、2つめがMMAを作る原料そのものを化石資源由来原料ではなく植物由来原料に変える取り組み、そして3つめが二酸化炭素からMMAの原料をつくるという取り組みです。
さらに、MCGでは、ケミカルリサイクルや植物由来原料によって作られたMMA、植物由来原料から発酵法により直接MMAモノマーを製造する新規製造技術によって作られたMMAを「サステイナブルMMA」と定義して、その開発に本格的に取り組んでいます。
まずは、ケミカルリサイクルについて説明します。PMMAのリサイクルを含め、使用済みプラスチックのリサイクルには、マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルがあります。マテリアルリサイクルは、使用済みプラスチックを熱でもう一度、柔らかくして、形も米粒状に変えてから、再び部品などの形状に成形します。端的に説明すると、使用済みプラスチックを融かして再成形し、別のプラスチック製品として再利用する方法です。回収された使用済みアクリル樹脂が劣化していたり、含まれる着色剤、添加剤の除去が困難なことから、元の品質や性能の維持が難しい点が指摘されています。
それに対してケミカルリサイクルは、使用済みプラスチックを化学的に分解し、元の原料やモノマーに戻す方法です。PMMAをMMAモノマーに戻せるのです。化学的な分解の過程で、不純物や着色に使った色素などをほぼすべて除去することができ、例えば黒いアクリル樹脂でもケミカルリサイクルをすると無色透明な原料に戻せます。
しかも、このモノマーは化石資源由来のモノマーと全く同じ品質管理のもとに作られる(リサイクルされる)ので、このモノマーから作られるアクリル樹脂も化石資源由来のものと全く同じ性能です。つまり、リサイクルの工程を経ても性能が劣化しないのです。そればかりか、何度、繰り返しても同じ特性を持ったものができるという、理想的なリサイクルといえます。
MCGでは、まずはこのPMMAのケミカルリサイクルを事業化することで環境負荷低減に貢献します。
それだけではありません。じつはプラスチック製品のケミカルリサクルを実現している方法は他にもありますが、当社でも実施している様に、その多くが使用済みプラスチックを「油化」しているのです。
― 確かに使用済みプラスチックから燃料を作るといったリサイクルの取り組みを聞いたことがあります。
長谷田:そうです。例えば、汎用プラスチックをナフサなどに戻してそこから基礎化学品やガソリンを作るといったケミカルリサクル(油化)です。この方法は、様々なプラスチックが一緒にリサイクルできるのですが、プラスチック製品の大元の原料であるナフサレベルまで戻すことになります。PMMAのケミカルリサイクルは、ナフサレベルまでは戻さず、「MMAモノマーに戻す」というリサイクルです。リサイクルの過程が短く、エネルギー効率の良いケミカルリサイクルなのです。わかりやすく言うと、アクリル樹脂の特性を活かして「アクリル樹脂をアクリルの原料に戻す」という効率の良いリサイクルです。但し、どんなプラスチックでも効率よくモノマーに戻せるわけではなく、PMMAはプラスチックの中でも、最もモノマーに戻しやすいプラスチックの一つなのです。
― 2つめの取り組みが植物由来原料からのMMAの製造ですね。
長谷田:MMAを作る原料を化石資源由来から植物由来の原料に切り替えようとしています。ケミカルリサイクルでPMMAの需要を100%まかなえればいいのですが、今後の需要の拡大を考えるとリサイクルとあわせて、新規にPMMAを製造することも必要です。そのときに、化石資源由来原料で作ってしまっては、結果的にCO₂排出量を大きく削減することはできないでしょう。そこで、植物由来の原料からMMAを製造し、PMMAを作る取り組みを進めています。
MCGグループは、MMAの製造法として「ACH法」、「C4法」、「Alpha法」という3つの製造方法※)を長きにわたって実用化してきた、世界唯一と言っても良いメーカーです。これら3つの製造法はそれぞれ、利用できる原料が異なります。1つの製造方法しか持たないメーカーでは、その製造方法では植物由来の原料が使えないといった場合もありますが、MCGは3つの製造方法のそれぞれで植物由来の原料が利用できるかどうかを検討できます。すでに、植物由来原料を既存の製造法に適用する技術開発を進めると共に、商業規模プラントへの適用を目指して取り組んでいます。
※)MMAの3つの製造方法についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
そして、3つめとして、MCGではCO₂を原料にMMAの原料となる基礎化学品を製造する技術の開発にも着手しています。2つめの取り組みで原料を全て植物由来に変えられたとしても、トウモロコシやサトウキビなど食料にもなる植物を大量に消費してしまって良いのか、食料にはならない植物でも安定的に一定量を確保することが可能なのかといったことも考慮しなければなりません。そこで、CO₂から製造されたMMAの原料の活用も構想されています。実用化までには、まだまだ道のりは長いものの重要な取り組みと考えています。

PMMAは「環境フレンドリー」な素材。魅力をアピールし、新規需要も創出を
― ケミカルリサイクルの取り組みでは本田技研工業やマイクロ波化学などと協業もしていますね。
長谷田:現在、MCGではケミカルリサイクルと植物由来の原料の利用という2つを中心に環境負荷低減の取り組みを進めていますが、特にケミカルリサイクルの手法にMCGならではの特徴があります。ケミカルリサイクルでは、高温でアクリルを熱分解する工程がありますが、その熱分解にマイクロウェーブを使っています。電子レンジと同じ技術ですが、ターゲットを直接温めることができるという特徴があります。コーヒーが入ったカップを電子レンジで温めると、カップは冷たいのにコーヒーが温まりますよね。あれは水の分子を直接温めているからです。
このマイクロウェーブの特性を活かし、無駄なエネルギーを使わずに使用済みのPMMAを効率的に熱分解しています。2023年には本田技研工業株式会社様の協力を得て自動車のテールランプなどに使用されたPMMAを回収し、マイクロ波化学株式会社様と共同でマイクロウェーブを活用したケミカルリサイクルにより再びテールランプに戻す水平リサイクルの実証実験に取り組みました。結果は良好で、化石資源由来の原料で作ったPMMAが使い終わって燃やされてしまうのと比べると、CO₂排出量を50%程度も削減できる見込みとなりました。
このマイクロウェーブでPMMAを効率的にケミカルリサイクルする技術を確立できているのが、MCGの大きなアドバンテージといえるでしょう。
― ここまで、MMA / PMMAのトップサプライヤーとして環境負荷低減やサステイナビリティを考慮した取り組みについてお聞きしてきました。今後、これまでの取り組みをどう発展させていきたいとお考えでしょうか。
長谷田:MCGグループは、ACH法、C4法、Alpha法の3つの製法を持っていること、そして、世界各地に拠点を持っていることで、原料の調達状況に大きく左右されることもなく、リーディングカンパニーとして安定供給を実現してきたことが大きな強みです。今後はさらにMMA / PMMAのリーディングカンパニーとして、環境負荷低減の取り組みとあわせて、もっとPMMAの認知度を高めるような取り組みにも注力していかなくてはならないと考えています。
その一環として、PMMAが環境フレンドリーな素材であることの啓発活動にも注力していこうと考えています。例えば、アクリルグッズ等再生利用促進協議会にも参画させていただき、話題のアニメーション東宝様の「薬屋のひとりごと」とのコラボレーションでリサイクルアクリルを使ったアクリルスタンドの販売や、キーホルダーの配布をしました。5月にパシフィコ横浜で、7月に名古屋で開催された「人とくるまのテクノロジー展」では、講談社様の「頭文字D(イニシャルD)」とのコラボレーションのアクリルキーホルダーを配布しました。
こうした取り組みを通じて、PMMAの認知度と、リサイクルに適した環境フレンドリーな素材であることをアピールしながら、新たな需要の創出につなげていきたいと考えています。

